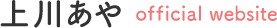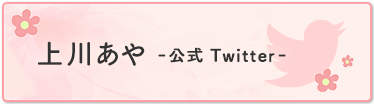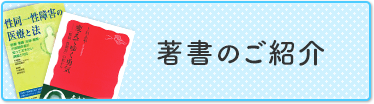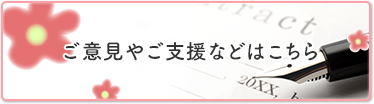◆上川あや
区の各行政計画が書く多様性の尊重がいかに視野が狭く、底も浅く、また立ち遅れたものであるかを本日は問いたいと思います。
まず、現在策定中の基本計画についてです。同計画は来年度からの八年間の行政運営の基本的指針であり、各部の行政計画をその傘下に束ねる最上位計画である。以上の理解に誤りはないでしょうか。
◎有馬 政策経営部長
委員御指摘のとおり、次期基本計画は、来年度からの八年間に区が重点的に取り組む政策、施策の方向性を明らかにした区政運営の基本的な指針であり、区の最上位の行政計画でございます。
◆上川あや
区は、二〇一八年成立の多様性尊重条例第七条で性自認、性的指向への差別を禁じ、第八条で、多様な性に対する理解の促進及び性の多様性に起因する日常生活の支障を取り除くための支援を区の条例施策として明記しています。
つまり、区の多様性尊重において性自認と性的指向は欠くことのできない属性であり、区の各部は、LGBTQゆえの困難があればそれを取り除く支援を行う責務を有している。以上の理解にも誤りはないでしょうか。
◎渡邉 生活文化政策部長
多様性を認め合い人権を尊重する地域社会を実現することを目指している区といたしましては、庁内各部が主体となって、性的マイノリティーの方々の困難を取り除く、そういった支援を行う責務があると認識してございます。
◆上川あや
ところがです。基本計画(素案)の本文で、性自認や性的指向が出てくるのは第三章、基本方針にただ一か所。言葉としては、「LGBTQ」、「性的指向」、「ジェンダーアイデンティティ」の三語が一度ずつ、性自認に至っては、その脚注で一度触れているのみとなっています。それでも、第四章、政策に具体的な記述があるのならまだ分かるのですが、その章にLGBTQ支援と分かる記述は一切存在していない。以上の認識に誤りはないでしょうか。
◎有馬 政策経営部長
次期基本計画(素案)では、計画の理念の一つに多様性を尊重し生かすことを位置づけ、その中でLGBTQなどの性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性について明記し、性自認については脚注で触れているものの、御指摘のとおり、各政策部分における多様性に関する内容の中にはこうした記述はございません。
◆上川あや
加えて、第四章の2、分野別政策の21、多様性の尊重において、区が対象として挙げるのは、年齢、性別、国籍、障害の有無という四つだけ。性自認も性的指向もLGBTQもありません。これは基本計画のみならず各分野別計画素案も同じで、区が多様性尊重で書くのは常にこの四つだけのように見えます。現計画の計画年度十年分の区と社会の大きな変化を全く捉えていないとしか思えず、一体何十年前の計画案ですかと問いたくなるような記述です。
区の多様性の捉え方がいかに時代遅れかは、各対人援助職の倫理綱領等と比較すると明らかです。日本医師会の医の倫理の基礎知識では、二〇一八年からLGBTが登場し、看護職、社会福祉士、ソーシャルワーカーの倫理綱領でも、日本社会学会、情報処理学会、日本保険学会の倫理綱領でも性自認と性的指向は明記をされ、そのほかにも、民族、宗教、出自、家族の在り方の記載もあるなど、多様です。
区の基本計画や各分野別計画における多様性尊重の対象は、もっと時代に追いつき、区の独自性、先進性を映したものとするべきです。また、各部が責務を負うLGBTQ支援も施策として明記をするべきです。御見解はいかがでしょうか。
◎有馬 政策経営部長
性の多様性の尊重については、大変重要な視点だと認識しており、計画全体を通して記載が徹底されておらず、配慮が足りない内容となってしまった点は大変申し訳なく思っております。
改めて次期基本計画(素案)の内容を確認し、記載を徹底するとともに、性の多様性の尊重をはじめとする計画の理念が庁内全体にしっかりと浸透するよう働きかけてまいります。
また、性の多様性の尊重に向けた取組については、担当所管部と連携し、御指摘の点も踏まえ、分野別政策の内容についてさらなる検討を進めてまいります。
◆上川あや
区教委の教育振興計画(素案)についてです。基本方針の3、多様性を受け入れ自分らしく生きるの記述にあるのは、ここでも、国籍、年齢、性別、障害、そして二つだけ、文化と言語を足しています。なぜ性自認や性的指向を書かないのでしょうか。
昨年、都内の認定NPOが十二歳から三十四歳のLGBTQを対象に調査をしたところ、十代では過去一年以内に自殺を考えた割合は四八・一%、実際に自殺未遂を経験した割合は一四%に達したと報じられました。国の自殺対策大綱でも、学齢期の性的マイノリティーはハイリスク層であると明記をされ、教員理解の重要性が特記をされています。
こうした子どものいじめや自殺予防に果たす教育の役割は重要であるのに、全く素通りする計画素案を看過できません。加筆を求めますけれども、いかがでしょうか。
◎知久 教育政策・生涯学習部長
今般素案としてお示しした教育振興基本計画におきましても、四つの基本方針の一つである多様性を受け入れ自分らしく生きるの考え方の中で「文化や言語、国籍、年齢、性別、障害の有無等に関わらず」との記載があり、またそのほか、素案の二か所に同じような記載がございます。性の多様性の尊重についても、ただ今申し上げた基本方針の多様性を受け入れ自分らしく生きるにつながる重要な要素であるにもかかわらず、明確な記述のない内容となっておりました。
先ほど政策経営部長からも答弁がありましたが、教育振興基本計画においても、素案の内容を精査し、計画案を策定する際に記述内容を改めてまいります。
◆上川あや
最後に、計画素案に書く多様性尊重で列挙するべき属性をさきに挙げた四つでよいとしたのは、ほかでもない多様性尊重条例やLGBTQ支援を所管する生活文化政策部だと聞きましたが、事実でしょうか。
◎渡邉 生活文化政策部長
全庁への指示はしてございませんけれども、各部から確認依頼があった際は、世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例の前文に「個人の尊厳を尊重し年齢、性別、国籍、障害の有無等にかかわらず」とございますので、この記述で統一してきたところでございます。
◆上川あや
LGBTQ支援を牽引するべき所管部が性自認、性的指向という要素を省略してよしとしていることは容認できません。今後は、多様性尊重条例の趣旨や、その多様性尊重の理念を書く際には必ず性自認と性的指向を明記するよう求めますけれども、いかがでしょう。
◎渡邉 生活文化政策部長
現在策定中の基本計画の基本方針には、そのような形、四つの属性に加えまして、性自認、性的指向についても記述してございます。配慮が足りないという御指摘を踏まえまして、今後は、多様性尊重の理念を記載する際には性自認や性的指向について明記するよう、また、支援施策の充実に努めるよう、早急に庁内各部に依頼してまいります。
◆上川あや
各所管の職務の中で実際に困難があるかどうかを…。