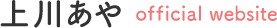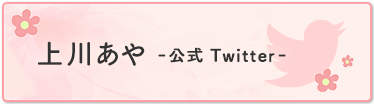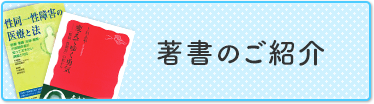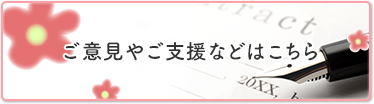◆上川あや
最後に、介護におけるLGBTQの困難についても触れます。
まず、同性カップルの介護といった場合には、結婚という制度がない中で、何をもって家族として認め、扱うのかということが、しばしば介護や医療の関係者間でも問題になります。トランスジェンダーであっても、身体、性自認、戸籍の性別が一致するとは限らない。こうした中で、その人の性が、同性介護という原則の中で、あるいは多床型の男女別に扱われがちな入所施設の中でどう扱われるのかといったことが懸念材料です。
私からこうした課題を提起して、世田谷区では全国に先駆け、介護職、医療職向けの性の多様性の理解研修を始めて三年目になりました。しかし、区が地道に理解者を増やしてきてくださる一方で、当事者から見ますと、理解ある介護人材、福祉人材がどこにいるのかいまだに区内で分かりません。ぜひこのギャップを埋める御努力をいただきたいのです。そこで、毎年区もその作成に協力している介護事業者ガイドブック、先ほどもお示しになられました「ハートページ」、こちらの世田谷区版で、区条例やパートナーシップ制度を紹介するページを加えて、研修済機関などの挿入ができれば安心できると思うんですけれども、いかがでしょうか。
◎谷澤 介護保険課長
介護サービスを利用する方にとって安心して事業者を選択できるように、御指摘の性の多様性にも配慮するべきと認識しております。そのため、このガイドブックの介護サービス事業所リストに、事業所ごとのLGBTQ研修の受講状況の掲載の可能性につきましては、編集発行事業者に打診をしてまいります。
また、次年度以降となりますが、行政情報として、多様性条例やパートナーシップ制度など、区の取組も掲載できるよう調整してまいります。
◆上川あや
ぜひお願いいたします。
所管に確認しましたところ、性の多様性理解に係る介護医療職研修で、受講された事業者が令和三年度九十六事業者百二十六名ということで、すばらしい取組をぜひ可視化してください。使える資源にならなければ意味がないと思います。終わります。