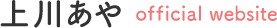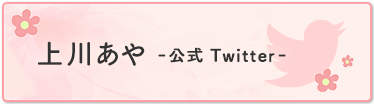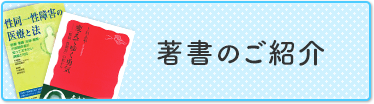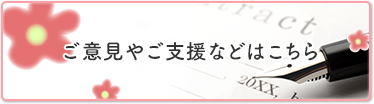◆上川あや
加齢に伴う難聴者が非常に多いのに、区政の聞こえへの支援が不十分である現状について伺います。
令和元年度の世田谷区高齢者ニーズ調査によると、聴力に支障がありますかという問いに二九・六%、およそ三〇%の高齢者が、はいと答えています。
この割合を一月現在の高齢者人口に掛けますと五万五千人以上と大変な数に上ります。ところが、それに見合った配慮があるとは言えない区政の現状をとても悲しく思います。この問題を、単に、だったら補聴器をすればよいと個人の問題にすり替える議論は誤りです。補聴器でしっかり聞こえる範囲は一般に一・五メートルと言われ、雑音の多い会議室や反響の多いホール等では用をなさないことははっきりしています。では、補聴器の限界ゆえにできることはないのかといえば、ちゃんとあります。なのに、必要な手だてが講じられていないのです。そこで、改めて求めるのがヒアリングループなどの補聴援助システムの活用です。例えば、ヒアリングループでは、必要な音声だけを直接補聴器や専用レシーバーに伝えます。補聴器ユーザーは、ヒアリングループのサインに気づいたら、音声モードをMからTに切り替えるだけ、これによって会議や講演、コンサート会場での発言者の声、音楽などがクリアに聞こえます。イギリスでは、公共施設や駅、病院、教会、果てはタクシーの中にまで備えられていることが珍しくないそうですが、区ではほとんど使われておりません。
区が昨年十二月に開催した人権週間記念事業、講演と映画の集いでは、よりユニバーサルな運営を求めた私の質問に応じて、新たに副音声と手話通訳と車椅子席が導入された一方で、私が質問の中で言及したヒアリングループの活用は見送られました。その理由について所管課は、ループは施設に付随する設備のため導入は難しいと文書で説明しましたが、全くおかしな言い訳です。
ヒアリングループには、あらかじめ床下などに埋設する固定型だけではなく、持ち運び可能な可搬式、携帯式があることが知られています。区でも私の議会質問に答え、二〇〇五年に世田谷総合支所がこの可搬式のループを購入、整備しております。先週その使用の可否を同支所に伺いますと、数年ぶりに改めて点検し、何ら問題なく使えるとの回答も得ています。ところが、区の人権週間を代表するイベントで、この可搬型のループは使われませんでした。区の人権週間に五万五千人を超える加齢性の難聴者は無関係でしょうか。また、今後も同イベントでは同じ無策を続けるおつもりなのでしょうか、見解を伺います。
◎内田 生涯学習部長
聴力に支障がある方の聞こえを補うヒアリングループにつきまして、今年度の人権週間事業、講演と映画の集いへの導入に至らず、利用を必要とされる皆様には大変申し訳なく思い、おわびを申し上げます。会場となる施設の設備等の確認を行ってきた中で、ホールを利用するに当たり、携帯型ヒアリングループの活用を進めるべく調整が不足しておりました。今後は、会場となる施設の設備等の状況と併せて、ヒアリングループ等、状況に適した機器を確保し、関係所管との連携調整を行い、活用に向けて取り組んでまいります。
◆上川あや
UD条例を所管する都市デザイン課に伺いますと、情報のユニバーサルデザインガイドラインでも、施設整備マニュアルでも、この補聴援助システムの役割を啓発している一方で、整備するかどうかは所管課次第、全体の整備状況については把握がないという御報告で驚きました。現在、九百三ある区の施設のうち、結局幾つの施設に同システムがあるでしょうか。通信方式と固定型か可搬型かも含め、御報告を求めます。
◎畝目 都市整備政策部長
現在、区内九百三の施設には学校や区営住宅なども含まれてございますが、委員お話しの補聴援助システム、集団補聴設備が備えられた施設について、改めて各施設管理者へ調査いたしましたところ、現在、固定型ヒアリングループが二施設、可搬型ヒアリングループが二施設、FM補聴設備が一施設、固定型ヒアリングループとFM補聴設備のある施設が一施設、赤外線補聴システムが一施設であり、合計七施設に設置してございます。
◆上川あや
現在九百三ある区の施設のうち七か所だけにあり、うち五か所はヒアリングループということです。
では、それぞれの施設に設置を示すピクトグラムの掲示はあるでしょうか。肝腎なシステムの存在を知らせずして、その利活用を申し出る施設利用者も、補聴器の音声モードを切り替える区民も現れるとは思いませんが、いかがですか。
◎畝目 都市整備政策部長
ヒアリングループは、磁気誘導コイルを使った集団補聴設備でございまして、正式なJIS規格のピクトグラムはございませんが、平成二十六年十月の全難聴福祉大会において決定されましたヒアリングループマークを、現在常設のヒアリングループを使用する三施設のうち一施設に掲出してございます。ヒアリングループは、補聴器や人工内耳の音声モードをTモードに切り替えることにより音声がよく聞こえるようになるものであり、この装置がある場所には、ヒアリングループマークも併せて設置することが望ましいと考えてございます。
区といたしましては、施設を利用する皆様が設備の有無について認識できるよう、事前の情報提供やマークの掲出、また様々なイベントにおいて、集団補聴設備等の普及に努めるなど、庁内関係所管に情報のユニバーサルデザインガイドラインの所管として、しっかり呼びかけてまいります。
◆上川あや
区の施設への整備状況は九百三施設に七か所で、何とけやきネットの集会施設には一か所もありません。つまり、五万五千人を超える高齢難聴者について、クリアに音声を聞ける施設というのは一つもないんですね。この現状を副区長はどのようにお考えになるでしょうか。
◎中村 副区長
高齢者の孤立防止や健康寿命延伸のためには、高齢者の社会参加の促進が必要と考えています。また、聴覚のバリアフリーを進め、周囲とのコミュニケーションの確保を図るという観点から、集会施設等における聞こえの支援に関する取組が重要であると認識をしています。御指摘の施設が高齢の難聴者の方に寄り添った状況になかったことについては、区として配慮が不十分だったと考えております。今後、高齢者が利用しやすい公共施設となるよう工夫をしてまいりたいと考えています。
◆上川あや
ならば、ぜひ次のように改善をお願いします。足立区など都内八区では、携帯型のヒアリングループを広く貸し出すことで、難聴者の社会参加を助けています。当区もまだまだ知られていない補聴援助システムの有用性を広く区民に伝え、その整備状況の発信とともに貸出しサービスを連動させて改善していただきたいと思います。一言お願いいたします。
◎山戸 高齢福祉部長
委員お話しの携帯型ヒアリングループの貸出しや補聴援助システムの有用性、使い方や設置施設等に関する効果的な広報、周知方法については、ほかの自治体の取組を参考にしつつ、総合支所をはじめとした施設所管等の関係所管との連携調整をし、検討を進め、最善を尽くしてまいります。
◆上川あや
生きている限り、誰もがひとしく歳を取りますので、私たちの未来です。七十歳以降の半数の人は聞こえないんですね。こういった困難を放置しないでください。個人の問題じゃありません、区の問題です。お願いいたします。終わります。