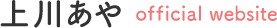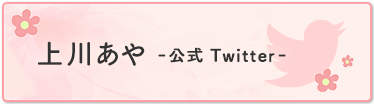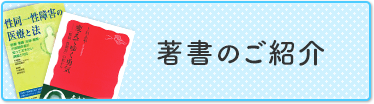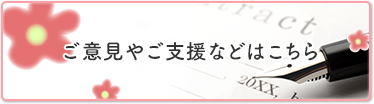◆上川あや
関東大震災時、区内でも起きた虐殺と、その過ちを伝え、教訓として生かす取組について伺います。
現在、区立の平和資料館では「関東大震災百年から考える災害と平和」と題し、烏山と太子堂で起きた朝鮮人殺傷に触れた企画展を開催しています。展示のきっかけは、二〇二一年九月以降、三度にわたり行った私の質問です。
当初の質問で、震災の直後、区内二か所で起きた朝鮮人殺傷の記録は、旧司法省の資料や、旧千歳村の村史、当時の世田谷町長の手記にも残るはずと確認を求めると、区もこれを認めました。ならば、区長がツイッターで私的に追悼するのみならず、区の意思で追悼をと求め続けて今回の企画展へと至りました。
朝鮮人虐殺をめぐっては、小池東京都知事が七年連続で追悼文送付を見送り、先月末には、松野官房長官も、政府内において事実関係を把握する記録は見当たらないと述べるなど、史実に向き合わない政治の動きが相次いでおります。こうした時世に、区内で起きた朝鮮人殺傷を認める企画展を開催した区の姿勢を評価いたします。しかし、その教訓を伝え、生かす上での課題はなお多いと考え、以下、伺います。まず、今回の企画展で、区は、区内で起きた殺傷事件の裏づけを三つの政府の資料に求めています。一つは、政府の中央防災会議、災害教訓の継承に関する専門調査会が示した報告書、二つ目に、当時は内務省の下部組織であった警視庁の大正大震火災誌、三つ目に、現在の公安調査庁の前身、法務府特別審査局が表した関東大震災の治安回顧です。
いずれの政府資料も、区内二か所で起きた朝鮮人殺傷を記録する一方で、官房長官は虐殺をめぐる記録は政府内に見当たらないと述べ、そごが生じています。私は、今回の企画展で区が根拠とした三文書は、いずれも政府が作成、保管、さらに公表してきた資料にほかならないと捉えておりますが、区はこれら三文書を作成した組織、機関をどのように捉え、また、どのように資料を入手されたのか、区の認識を問います。次に、区立の郷土資料館にも二つの殺傷事件の発生を裏づける区の別資料や、デマに踊らされ大混乱に陥った当時の地域を知らせる証言記録、また、周辺の古写真等があるのに何一つ展示がないのは残念でした。
加えて、平素は善良であった住民がなぜこうもデマを信じ、自警団を組織し、凶器を手に朝鮮人らを襲い、死に至らしめたのか、それらを考察する上で不可欠な当時の植民地支配という背景、独立抵抗運動への恐れ、朝鮮人一般に対しての差別や偏見を伝える展示が全くないことも残念でした。この点、歴史の専門調査員が配置をされ、多くの資料を所蔵する郷土資料館との連携があれば、より奥行きのある学びの深い展示になったのではないでしょうか。
また、区は今回の企画展を一過性に終わらせず、歴史の教訓として区民に、また、後世に伝え続けるといいます。ならば、平和資料館と郷土資料館との連携はますます重要になると考えます。併せて区の見解を問います。次に、区史編さん事業への反映です。
一九七六年に区が発行した「世田谷近・現代史」は、当時の虐殺について、暴徒と化した乱衆の、当時の社会において、最も非力な人々に対する暴虐は、償い難い罪業として歴史に残されるのは当然のことであると強く非難しながらも、世田谷地域では、かかる殺傷事件が発生したとの記録は見つかっていないとして素通りをしました。当時から烏山で起きた事件は知られ、また、存命の関係者もいらした時代の記述として不自然です。また、同記述の直前、世田谷町長がその手記で、「三軒茶屋ニテ殺傷事件アリ」と書いたことを紹介しているにもかかわらず、全く不釣り合いな記述です。他方、一九八二年発行の区制五十周年記念「世田谷、町村のおいたち」では、一転、烏山での殺傷を実際にあった事件と書き、犠牲者数を十三名としています。しかし、現在の目から見れば、どちらの記述も不適切、あるいはミスリードではないのでしょうか。
また、現在作業中の区史編さん事業では、殺傷の過ちを率直に認め、より正確な記述を求めますけれども、いかがでしょうか、見解を問います。次に、区教委に確認をしたところ、現在の区立小中学校の教科書には、関東大震災時の根拠のないうわさや流言が元で多数の朝鮮人や中国人などが殺されました等の記述があると分かりました。しかし、先生方自身がこの町で起きた悲劇も知らずに教えるというのはいかがなものでしょうか。
子どもたちへの教育で、じかに地元の悲劇に触れることは難しくても、教職員への人権研修では事実を伝え、学びを深める材料とするべきです。現に関東大震災時、現在の市の範囲で八十九名もの虐殺犠牲者を出した埼玉県本庄市では、必ず新任、転任の教職員研修で伝えているといいます。区教委にも同様の対処を求めますけれども、いかがでしょうか。
また、区長部局でも人権研修は、採用一年目研修を始め、七年目以降も五年ごとに受けるなど重視をされています。これら研修でもぜひこの町で起きた悲劇を伝え、特にヘイトスピーチの害悪に理解を深める材料としていただくよう求めます。区の見解を問います。次に、生涯学習についてです。
現在の価値観において平和は、単に戦争がない状態のみを指すのではなく、暴力のない状態までをも含む理解が広がりつつあります。災害時、デマをきっかけに平素からの偏見に火がつき、不信や懸念が高まると、やがては防御を名目に制御が利かず、暴行や殺害にまで至るという過去の教訓は、区のピースセミナーでも取り上げてよいテーマだと考えます。区教委の生涯学習でも、その教訓を生かした取組を求めますけれども、いかがでしょうか。次に、災害対策です。
さきに挙げた政府の中央防災会議の報告書は、関東大震災全体の死者十万五千人のうち千人から数千人を殺害によるものと推計をし、次のように書いています。武器を持った多数者が非武装の少数者に暴行を加えた挙句に殺害するという虐殺という表現が妥当する例が多かった。加害者の形態は官憲によるものから、官憲が保護している被害者を、官憲の抵抗を排除して民間人が殺害したものまで多様であるとして、官憲の記憶に残る殺傷事件の死者数一覧表までを公表した上で、こう総括をしています。自然災害がこれほどの規模で人為的な殺傷行為を誘発した例は、日本の災害史上、他に確認できず、大規模災害時に発生した最悪の事態として、今後の防災活動においても念頭に置く必要がある。引用はここまでです。
ところが、危機管理部に確認をしたところ、区の地域防災計画におけるデマへの対処の記述は、震災編第四部南海トラフ地震等防災対策のみに書かれ、他の計画部分には記載がないと分かりました。流言による混乱を防止し、正しい情報を発信することを防災計画全体に通底するものとして、しっかり記述するよう求め、見解を問います。
最後に、企画展に寄せられた区長のメッセージについてです。
企画展の順路の最後に区長のメッセージのパネルがあり、朝鮮半島出身者を狙った襲撃や撲殺事件が起きたことも忘れないでいたいと思いますと、虐殺を率直に認めた姿勢を評価しています。しかし、そこに続く言葉には引っかかりを覚えました。いわく関東大震災という大きな災害を通じて、命と人権の貴さに思いをはせ、犠牲となられた方々に心からの追悼を捧げるとして、震災そのものの犠牲者と、デマで汚名を着せられ、人の手で殺された犠牲者とを分けることなく追悼しているのです。
虐殺犠牲者への追悼文送付を見送り続け、強い批判を受けてきた東京都知事も、東京都慰霊堂で行われる大法要に追悼文を送付していることをもって、全ての方々に追悼の意を表していると、逃げ口上を繰り返しております。この夏も繰り返された同じ言い訳に、朝鮮人犠牲者追悼式典の実行委員長が、一緒くたにしてよいのかと批判をしたことを区長も御存じではないかと思うのです。ここは震災による犠牲者と、虐殺という人災の犠牲者とを明確に分け、別の言葉があってもよかったと考えるのですが、いかがでしょうか。
区長の真意をお尋ねし、壇上からの質問を終わります。
◎保坂 区長
上川議員にお答えをいたします。
関東大震災、区内でも起きた虐殺事件、そして、私のメッセージについての表現についても御質問がございました。
本年九月一日、私は、その日より開催される平和資料館の企画展の中で、関東大震災から百年の節目を迎えるに当たってのメッセージを書き、これが掲示されました。
初めに、九月一日が災害への認識と備えの強化のための防災の日と制定されていることから、冒頭、関東大震災全体の被害状況と、犠牲になられた方々に対する思いを表明しております。加えて、震災直後の混乱の中で流言飛語が飛び交い、朝鮮半島出身者等を狙った襲撃や撲殺事件が起きてしまったことについて、痛恨の極みであり、二度と繰り返してはならない出来事として忘れないでいたいという思いを表明をいたしました。
この二点について明確にした上で、追悼の意の表明について、お一人お一人の命や尊厳の重みを真摯に受け止め、犠牲に遭われた全ての方々に思いを巡らせて書いたものでございます。
今後、どのような理由にせよ、犠牲者を出してはならないという考えの下、区民の尊厳に配慮した災害対策のさらなる強化に取り組むという決意を込めたものでございます。
議員お話しのように、地震による建物の倒壊や火災の延焼による死者と、一方、デマにより虐殺された死者への追悼をまとめてするのではなく、それぞれ別々に言及すべきではないかという御意見は受け止めさせていただき、今後の参考にしたいと思います。
◎渡邉 生活文化政策部長
私からは、平和資料館での企画展に関連しまして、三点御答弁申し上げます。
まず、今回の企画展において使用しました資料や写真についてでございます。
今回の企画展は、災害により平穏な生活が崩壊し、混沌とした状況下にあっても、助け合う精神を保ちながら冷静な判断と行動ができるか、その上で、他者の人権、尊厳を大切にすることができるかという視点から、より多くの区民の皆様に災害時における平和について考えていただくことを目的に、今月の一日から三十日まで公開しているものでございます。
展示に使用しました写真や資料につきましては誰もが閲覧、入手可能な状況にあるものですが、そのうち中央防災会議、災害教訓の継承に関する専門調査会の報告書は内閣府のホームページで公開されているものを、また、警視庁、大正大震火災誌と、法務府特別審査局の関東大震災の治安回顧につきましては、国立国会図書館デジタルコレクションを活用し、参考とさせていただきました。
これらの資料につきまして、中央防災会議は現在の内閣府の会議体、警視庁は、現在の東京都の組織ではなく当時の内務省の地方官庁、法務府特別審査局は、現在の法務省の前身である昭和二十五年前後に設置されていた法務府内の組織としての認識で使用してございます。続けて、郷土資料館との連携があれば、より学び深い展示になったのではないかという点についてでございます。
今回の展示の企画や資料作成におきまして、平和資料館の専門員が御指摘の郷土資料館に出向き、郷土資料館の学芸員と意見、情報交換などを行ってございます。加えて、災害対策課や広報広聴課、そして、東京都復興記念館などからもお話を伺い、情報の収集や資料の提供を受けたことや、その他多くの文献を参照しながら、初めてこの事件を知る方にも分かりやすく、平和な状態とは何かを考えていただけるよう、企画展の内容や構成、方法等について検討したところでございます。
今回の郷土資料館との連携、協力を通じ、郷土資料館が有する見識や資料について改めて知るきっかけとなりましたが、あらかじめそれらをうまく融合できれば、議員お話しのように、より学び深い展示の工夫もできたものと考えてございます。
今回は初めて実施した企画展でしたので、今後も御質問の趣旨を踏まえ、資料や構成について郷土資料館とも連携しながら工夫してまいりたいと考えてございます。最後に、今回の企画展を一過性に終わらせず、歴史の教訓として区民に、そして、後世に伝え続けるための今後の平和資料館の取組についてでございます。
今回、関東大震災から百年目の節目に合わせて実施した企画展ですが、この殺傷事件につきましては、引き続き後世に伝えていく必要があると認識してございます。
したがって、今後も折に触れ、関東大震災とともに取り上げてまいりたいと考えてございます。また、今回の企画展において既に来館者等から多くの意見や感想をいただいておりますので、これらと併せて、今後、郷土資料館をはじめ、関係する機関とも連携する研究や収蔵資料等についての連携をさらに図りながら、より学び深い企画運営と情報発信にも努めてまいります。以上でございます。
◎有馬 政策経営部長
私からは、二点お答えいたします。
初めに、一九七六年発行の「世田谷近・現代史」、一九八二年発行の区制五十周年記念「世田谷、町村のおいたち」の記述も不適切、または不十分なのではないかという御質問にお答えいたします。
一九七六年に刊行した「世田谷近・現代史」では、関東大震災と区内の開発という章立ての中で、被災後の混乱と住民の対応というタイトルで、関東大震災時に起こった流言飛語について取り上げておりますが、その中では、議員御指摘のとおり、世田谷地域においては、今までのところかかる殺傷事件が発生したとの記録が見つかっていないと記述しております。
一九八二年に刊行された「世田谷、町村のおいたち」では、村から町へというタイトルで粕谷村を紹介した中で、関東大震災時で起こった流言飛語について、朝鮮人殺傷事件は烏山で起きましたと記述しております。当時の執筆に当たり、東京百年史や入手できた記録から執筆に至ったことが刊行物から読み解けることから、各執筆者は、その当時知り得た史実などの情報を基に調査研究し、執筆したものと考えております。次に、現在作業中の区史編さんで正確な記述をについてお答えいたします。
世田谷区史の編さんに当たっては、時代別、原始・古代史、中世史、近世史、近現代史の四つの編さん委員会に分かれ、刊行に向けて調査研究、執筆を進めていくことになります。関東大震災をテーマとした記述は近現代史の中で取り上げることになりますが、令和六年四月に近代史の委員会の委員に正式に執筆をお願いし、令和八年度に刊行する予定となっております。
執筆に当たっては、編さん委員会の中で章立て等を整理し、項目ごとに担当執筆者が原稿を作成し、委員会の中で議論して最終原稿を練り上げていくことになります。
区としましては、これまで刊行した区史のほか、今回の企画展に合わせ、平和資料館等で収集した資料や展示内容等の情報など、必要な情報を提供しながら、時代に即した世田谷区史となるよう、各執筆者と協力しながら編さんに取り組んでまいります。以上でございます。
◎宇都宮 教育総合センター長
私からは、教員への人権研修についてお答えをいたします。
教育委員会では、教員の人権意識を高めるために、転入、新任管理職や、十一年目を過ぎた中堅教員、新規採用教員、人権教育担当教員を対象として人権研修を実施しております。また、校内では、年度初めに東京都教育委員会作成の人権教育プログラムを活用して人権研修会を実施することで人権感覚のさらなる醸成を図っております。
現在、人権研修の中で、子どもや外国人などをはじめ、様々な人権課題に関わる差別意識の解消を図るための研修を行っております。
今後、人権研修会等において、関東大震災時に朝鮮人殺傷事件が区内で起きたという事実を伝え、人権、尊厳を大切にすることの重要性を伝えてまいります。以上です。
◎池田 総務部長
私からは、職員研修における事件の取扱いについて御答弁いたします。
職員には高い人権意識に裏づけされた職務遂行が求められており、区では、新規採用時や採用後五年ごとの節目の機会を捉え、人権研修を継続的に実施し、職員が障害や性別などによる差別、外国人の人権問題などに対して正しい理解を得ることができるよう取り組んでいるところでございます。
この人権研修の中におきまして、関東大震災直後に区内でも流言飛語が広がり、朝鮮人殺傷事件が起こった事実について伝え、ヘイトスピーチの害悪と他者の人権、尊厳を大切にすることの重要性を伝えてまいります。以上でございます。
◎知久 教育政策・生涯学習部長
私からは、区のピースセミナーにおいても取り上げられるべき内容ではないかについて御答弁いたします。
ピースセミナーは、昭和六十年の世田谷区平和都市宣言で掲げた核兵器の廃絶と世界に平和の輪を広げることを目的に、平成二年より様々な講師を招き、戦争体験や平和に関する講話を聞く座学式の講座や、区内または周辺の戦争遺跡や資料館を見学するフィールドワークなど、区民の平和学習の場として実施してまいりました。
より広い意味での平和を実現するためには、戦争の悲惨さや平和の大切さなどを学び、後世に伝えるだけでなく、震災時の痛ましい悲劇を風化させずに、常に向き合い、教訓を学び、伝えるとともに、誰もが他人の人権を尊重し、お互いに配慮した行動を取ることも大切であると考えております。
こうした考え方の下、議員の御提案につきましては、ピースセミナー参加者が望む学習テーマに関する意見等もお聞きしながら検討してまいります。以上でございます。
◎大塚 危機管理部長
私からは、流言飛語による混乱を防止し、正しい情報を発信することを地域防災計画に記述することについて御答弁申し上げます。
発災後の社会不安が蔓延する状況下におきましては様々な情報が飛び交うこととなり、特にSNS等を通じて多くの情報が拡散される現代では、一たび発信されたデマや流言等についても瞬発的に拡散されるリスクが高まっていると考えております。こうしたデマ情報等が発信、拡散されることは社会全体に及ぼす影響も大きなものとなり、区民生活の混乱回避のためには積極的な注意喚起が必要であると考えております。
災害時において、デマ情報等を打ち消すための情報発信を行うことなどについて、事前に計画に定めておくことは意義あることであり、今後、都や警察などの関係機関とも役割等について確認し、地域防災計画の修正の際に、その位置づけについて検討してまいります。以上です。
◆上川あや
それぞれ御答弁ありがとうございました。区長よりいただいた御答弁で、区長のメッセージに込めた真意ですとか誠意も感じましたので、ありがとうございます。また、生活文化政策部長の御答弁で、今回の企画展における区内で起きた朝鮮人虐殺の展示は、国の資料、国の記録に基づくものと確認ができました。
まだ伺いたいことがございますけれども、その余は決算特別委員会で伺えればと思います。
終わります。