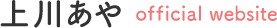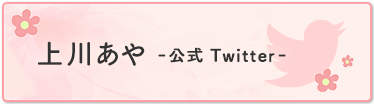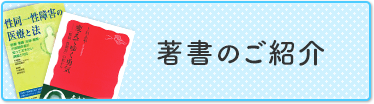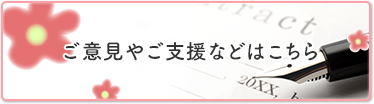◆上川あや
最後に、空襲被害者への支援についてです。
この春の私の質疑に応え、区はさきの大戦の空襲被害者等に見舞金を支給するなど独自の支援策を検討する姿勢を明らかにされました。しかし、直後のNHKでは、区は、区内に住み、空襲や艦砲射撃などでけがをし、障害が残った人にのみ見舞金を支給する想定と報道されており、それでは支援の対象が狭過ぎないかと懸念しています。
前回の質問を通し、私は両手に焼夷弾で重度のやけどを負い、戦後、三度の手術を繰り返しながらも御不自由はなお残り、それでも都から障害者手帳の交付は受けられず悔しかったと話された区内の高齢男性や、終戦の年、本区を襲った山手空襲の焼夷弾の直撃で祖母を失った昨年度まで皆さんと共に働かれていた区の幹部OBの方とお母様、また、実の親が戦争で御両親共失った戦災孤児だと明かしてくださった区の現役幹部のそれぞれにお会いし、お話を伺う機会を得ましたが、前述の基準に従えば、それら全員が区の支援対象から漏れ出ることになります。
とりわけ、幼くして両親、保護者を奪われた戦災孤児の悲しみや、戦後も長く続いたであろう御苦労が区のお見舞い対象から外れてよいとはとても思えませんし、戦争で傷を負った民間人の支援を区でなさるというならば、障害者手帳がなくても、日常生活や社会生活で支援を必要とする人を障害者等と定めて施策を講じる世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例にのっとり、一人一人が心身に負ったハンデに着目した支援とするべきです。
以上、戦災孤児への対応と障害者手帳のない傷病者への対応の二点、区の支援対象から漏らすことがないよう区の見解を求め、私の壇上からの質問を終わります。
◎保坂 区長
上川議員にお答えをいたします。
空襲被害者支援の在り方についてでございます。
世田谷区におきましては、昭和五十年、一九七五年より、原爆被爆者に対する見舞金、昭和六十年、一九八五年には平和都市宣言、平成七年、一九九五年には、世田谷平和資料室、そして十年前、戦後七十年の節目となる平成二十七年、二〇一五年に、平和資料室を平和資料館としてバージョンアップをしてまいりました。さきの大戦に関し独自の取組を行い、戦争の悲惨さを伝え、恒久平和を願い、区民に伝えてまいりました。
今回、区として空襲等被害者の支援の在り方についての検討を始めてきたところですが、国会では、超党派国会議員の手による法案作成の動きがございますが、まだ法律の制定が見通すことができず、他自治体では、既に独自に見舞金を支給している例もあって、地方自治体として、この検討を開始することは、時期にかなった意義のあることと考えております。
先ほど紹介しました超党派国会議員による法律要綱案、これは幾多変遷がございまして、最新のものなども見ておりますけれども、あるいは、名古屋市などの先行事例も検証をしまして、長年の間、被害に苦しまれてきた当事者に寄り添い、区としては、現在の世田谷区民が対象であることを基本としながら、その制度設計の詳しい枠組みについては、戦災孤児や空襲における障害者手帳の有無についても含め、有識者等の御意見をいただきながら検討を進めているところです。
ヨーロッパ各国では、第二次世界大戦での民間人への被害補償を国家が行っております。戦争被害に対しての補償は国の責任で行うべきであることは言うまでもありません。ただし、それが八十年の長きにわたって実現をしていない、これも事実でありまして、区はこれらの補償とは別に支援を検討するものであります。戦後八十年となり、戦争被害者の高齢化が進んでおります。残された時間は、残り少ないと言えます。世田谷区でこのような取組を進めること、検討していること自体、国がさらにしっかり前向きにこの問題に取り組むよう促すということも併せて望んでおります。以上です。
◆上川あや
再質問いたします。空襲被害者支援についてです。
検討されるということで、前向きなことは分かったんですが、スケジュール感が見えません。いつぐらいに何をなさるのか、スケジュール感をお示しください。
◎保坂 区長
上川議員の再質問にお答えします。
先日、他会派でも答弁させていただきましたが、これから調査、論点整備、範囲を決め、どういう選択肢があるのか、これを有識者のお話を伺いつつ、戦後八十年というタイミングが来ておりますので、このタイミングを意識してフレームを示していきたいと考えています。
高齢化が進む中で、空襲の被害に遭った方という意味では、大変長いことこの問題を放置されてきたわけで、この被害の心情にも寄り添いながら、この機会にどうするかという結論を、検討を重ねながら、その機運を逃さずに取り組んでいきたいというふうに考えております。
◆上川あや
超党派議連の法案の提出も見通せず、仮に通っても、払われるのは障害や顔にケロイドがある方々への一律五十万円だそうです。本来あるべき補償には程遠く、遺族補償は戦災孤児を含めて全くありません。こうした中、国、自治体ともに無策であることは、今後政府の行いで起こる戦争で、また私たち民間人が巻き込まれても、政府は補償せず、また自治体も支援をせず、ただ、我慢をせよと強いるそんな繰り返しの先例につながります。
その意味で、私は被害者を放置できないだけではなく、この国の戦災補償の在り方と、私たち自身の未来を懸念しています。ぜひこのあたりも御理解いただいて、議員の皆さん方にも十分、お年を召されている被害者の方々への支援に御理解と御厚情をいただけたらと思っています。