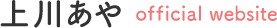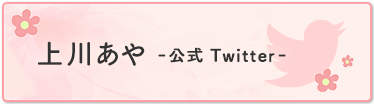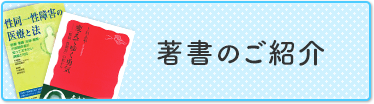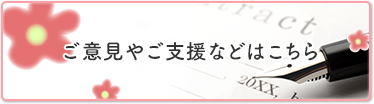◆上川あや
次に、区の文化芸術振興策に関し、二点提案をいたします。
提案の一つ目は、感覚過敏のある方々への合理的配慮です。
感覚過敏とは、音や光などの感覚が過剰に敏感になり、日常生活に支障を来たす状態を指し、精神障害、知的障害のある方にも見られる一方で、特に発達障害との関連が指摘をされています。多くの人にとって心地よい光でもまぶしく感じたり、さほど気にならないざわめきにも苦痛を覚えたりします。このため、平均的な感覚に合わせて調整された光や音でも体調を崩したりパニックになったりし、周囲からは理解されづらく、人知れず困っている人も多いとされています。
こうした方々への配慮として、今、国内の美術館、博物館にも広がりつつあるのがセンサリーマップの公開です。これは、音や光といった感覚情報をあらかじめ整理、公開することで、感覚過敏のある人やその家族、引率者にも対策を立てやすく、また、共に楽しく過ごしていただきやすくするもので、国内では二〇二三年にマップ公開した東京国立博物館がその先鞭をつけたとされています。
同館が取組を始めたきっかけは、同館職員が訪ねたイギリスで、小さな町にもセンサリーマップの公開が広がる事情に触れたこと。同館のセンサリーマップは先行する大英博物館やシンガポール博物館のものを参考に国内当事者の意見も入れて作られ、その後、同種の取組は七館ある全ての国立博物館へ、また、上野動物園や関西万博会場にも広がりを見せています。
区でもそれらを参考に、ぜひ遅れることなく、感覚過敏への合理的配慮を検討するべきです。まずは、その手始めに、区立の美術館、文学館からセンサリーマップの公開を求めますがいかがかでしょうか、区の見解を問います。
◎渡邉 生活文化政策部長
次に、センサリーマップの作成、公開についてでございます。
区では、第四期文化・芸術振興計画の基本目標に、区民が文化・芸術を身近に感じられる取組の充実を掲げ、誰もが文化芸術の楽しさや魅力に触れる機会の創出に取り組んでいるところでございます。お話しにございましたセンサリーマップですけれども、感覚過敏や感覚特性がある方にとりまして、音や光、においなどの苦手な場所を回避したり、事前に対策を考えて施設を訪れることが可能になってまいりますので、区においても有用なものと認識してございます。
御紹介のございましたマップを導入している東京国立博物館に確認したところ、作成の際には当事者の方に御協力もいただいて、実際に館内を回って御意見を伺ったり、大学の研究チームにも、光や音の影響度を専門的な見地から調査していただくなどし、約一年の工程を経て公開に至ったということでございます。
区といたしましては、こうした観点も踏まえ、センサリーマップの策定に向けて美術館及び文学館と具体の調整を進めるなど、区民が安心して快適に鑑賞できる環境整備に取り組んでまいります。