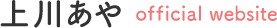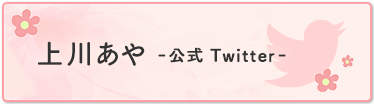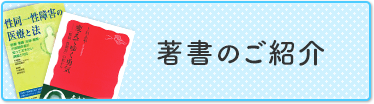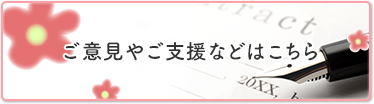◆上川あや
初めに、不登校の学齢生徒も学べる、通える夜間中学への展開を求めて伺います。
今回、私が特に重視をしているのは、不登校の約三割から四割を占めるとされる起立性調節障害のある子どもたちへの学びの保障です。
まず、この起立性調節障害のある生徒の特徴を、福島県立医科大学が同県教委の後援を得て全県立高校生徒に配付した健康づくり広報紙「いごころ」の一部抜粋から以下、御紹介したいと思います。起立性調節障害のある人は、午前中に症状が強く現れ、午後になると軽くなり、夜は活発に動けるようになります。そのため、朝は起きられない、起きてもぼうっとしている、何とか学校に行っても遅刻する、午前中は居眠りしてしまう、それなのに午後は少しずつ活動的になり、帰宅後はすっかり元気で、夜はなかなか寝つけない。家族は、夜遅くまで起きているから朝起きられないと考え、学校では遅刻常習犯、授業中も寝ている怠け者と思われ、友達ともあまり交流できなくなります。やがて授業の内容についていけないなどの理由で、不登校になることも少なくありません。引用は以上です。
同障害への理解促進と支援が求められた他会派の質問に、この六月、教育センター長は次のように御答弁されています。
令和四年度に実施した不登校支援ガイドライン策定のためのニーズ調査では、不登校児童生徒約千五百名に対し、不登校に至った要因について尋ねました。その中で約五百名が体の不調を不登校の要因に挙げており、中には起立性調節障害を罹患しているケースもあると認識しています。この病気は、日本小児心身医学会の発表では、軽症例を含めると小学生の約五%、中学生の約一〇%が罹患しているとされていますとまず基本認識を示された上で、学校と協力して保護者の理解を広げる方法を検討してまいりますとの言葉で締められました。
学校から保護者へと理解を広げるのはよいことです。しかし、その病気ゆえに、朝起きることや日中活動に難のある子どもたちに、区教委は朝から学ぶ義務教育しか提供していない。そこで、本来求められる合理的配慮を私は今回の質問で掘り下げたいのです。
さきの答弁で区教委は、日本小児心身医学会の発表では、軽症例を含めると中学生の約一〇%が罹患しているとされた。これを五月一日現在の全区立中学校の生徒数に当てはめますと、千二百人弱もの生徒が罹患者です。また、同学会は、不登校の三割から四割に同障害が併存するとし、重症例を全体の一%としています。これを令和四年度の全区立中学の不登校数、八百十五人に当てはめると、二百四十五人から三百二十五人が不登校生の罹患者です。全区立中学生の一%なら百二十人もの生徒が重症者です。ところが、区教委は朝から学ぶ学校しか提供しないのです。かつて夜間中学は、学齢期を過ぎた十六歳以上を受入れ対象としましたが、文科省は令和元年十月、不登校児童生徒への支援の在り方についてと題した通知でこれを改め、今では不登校・学齢生徒の受入れも可能としています。
さらに、文科省が公開している夜間中学設置応援資料「夜中を全国に!」では、学齢生徒の夜間中学での受入れについて、具体的に次の二つの方法を示しています。
一つは、日中の在籍校に籍を置いたまま、夜間中学で受入れ、出席扱いとする方法。二つ目は、夜間中学を文科省の不登校特例校とし、入学、転入そのものを認める方法です。
加えて、文科省が昨年一月に出した夜間中学の設置・充実に向けて【手引】の第三次改訂版では、教育機会確保法第十四条、地方公共団体における就学の機会の提供等から求められる自治体の対応について次のように書いています。既に夜間中学を設置している地方公共団体においても、個々の生徒のニーズを踏まえ、生徒の年齢、経験等の実情に応じた教育課程・指導上の工夫を図るとともに、不登校となっている学齢生徒の受入れなど、実質的に十分な教育を受けられていない多様な生徒の受入れについても検討することが求められます。引用は以上です。ところが、区教委は、ここで求められた夜間中学への受入れの検討をいまだしておらず、ただ保護者の理解を広めると言うのです。学べる場の保障がございません。
以上を踏まえ、五点伺います。第一に、現状の朝から学ぶ区立中学だけでは、重度の起立性調節障害のある生徒に学びを保障できないのではないでしょうか。見解を問います。
第二に、区が開設予定の不登校特例校も、登校時間を朝九時に、授業の開始を九時三十五分からとしておりますが、不登校に多い起立性調節障害の生徒には依然、合理的配慮のない学習環境の設定ではないのか、後ろ倒しにはできないのか、併せて伺います。
第三に、不登校の学齢生徒、保護者が求める夜間中学への登校ニーズです。既に区教委には、鳥取県教委、愛知県教委が行った不登校の学齢生徒、その保護者を含めた夜間中学への通学ニーズ調査の結果を御紹介しております。学齢期を含めた区分では、ともに約二割の生徒が夜間中学への通学を希望しています。この二割を本区の不登校中学生に当てはめれば約百六十人となります。また、鳥取県教委が県内三か所の教育支援センター、当区のほっとスクールに当たる機関の利用者に調査した結果でも、夜間中学に通ってみたいとした生徒の割合は何と三二%、三人に一人です。通わせてみたいとした保護者も五七%、実に三人に二人という高率でした。これら先行調査の結果からはその潜在需要は決して小さくないと考えますが、区教委の評価はいかがでしょうか。
第四に、本区の夜間中学の門戸を学齢期の生徒にも開くことです。まず、さきに挙げた二つの受入れ手法の一方、夜間中学を文科省の不登校特例校とし、学齢生徒の入学、転入も認める手法は、既に香川県三豊市立と福岡県大牟田市立の夜間中学で実現し、既に学齢生徒が通い始めております。また、来年度開設予定の三重県立夜間中学もこれに続く見通しです。
残るもう一方の手法、日中の在籍校に籍を残しつつ、夜間中学で受け入れ、出席を認める手法も、千葉県松戸市教委が、今年度既設の夜間中学に取り入れる意向を表明し、来年度開設予定の三重県立夜間中学と名古屋市立の夜間中学でも導入の予定です。
本区も、今挙げた二つの手法のいずれか、あるいは両方を取り入れ、不登校の学齢期生徒に夕方から学べる選択肢を用意できたらと願いますが、区教委の見解はいかがでしょうか。
この質問の最後に、夜間中学という手法に限らず、本区が掲げる一人の子どもも置き去りにしないという見地から、起立性調節障害のある児童生徒への学びの保障をいかにお考えになるのか、教育長のお考えを伺えればと思います。
◎知久 教育長
私からは、起立性調節障害のある児童生徒への学びの保障についてお答えいたします。
不登校児童生徒が増加していますが、その中で、起立性調節障害を含め、体調が優れず、登校できないでいる児童生徒が一定数いることは認識しております。こうした児童生徒に対し、学習機会を確保するとともに、友人や地域との関係性も考慮しつつ、学びを継続できるよう配慮することは、教育委員会、学校の課題と捉えています。
当事者が体調の不良を理解されず、単に無気力のように思われ、悩んでいるなどの事例があると言われていることから、まずは、当事者を含め、学校、保護者へ起立性調節障害等の症状を周知し、理解を促すとともに、実際の教育に関わる対策については、支援を求める当事者の声を聞き、適切な配慮を行うよう、学校、教育委員会ともに取り組んでまいります。
詳細は部長より答弁をさせます。
◎宇都宮 教育総合センター長
私からは、起立性調節障害等による不登校生徒も通える夜間中学について五点御答弁申し上げます。
まず、御紹介いただきましたとおり、不登校児童生徒の中には、起立性調節障害等、体の不調が原因で登校が安定しない方もいるということを認識しております。午後あるいは夕方には体調が回復するが、特に午前中の通学が難しいという児童生徒に対し、どのように学習機会を確保し、通学、進学に結びつけていくかは、教育委員会として取り組むべき課題と捉えています。
次に、起立性調節障害等、体の不調で通学が困難な児童生徒に向けては、まず、遅刻等が決して無気力によるものではないことを担任はじめ教職員が理解し、同級生を含め周囲の協力を得られるように配慮することが必要です。既に出席の扱いについては通知を出し、当事者の努力を最大限認めていく方針を示しています。また、学習の遅れが懸念される場合、当人や保護者と相談しながら、支援の体制を取り、学習機会を確保できるように努めるなど、在籍校での理解と配慮により、地域の学校で卒業、進学できるよう支援してまいります。
また、夜間学級の活用についての御提案をいただきました。既存の夜間学級を特例校として学齢期の生徒の転校を受け入れることを想定すると、現在の夜間学級の時間だけでは授業時間数が確保できず、ほかの自治体の事例のように早く始めると教室が競合いたします。特例校としての教育課程についても、現在の在校生との調整が必要なことや、下校時の安全確保についても課題となります。一方で、不登校生徒を夜間学級で受け止め、在籍校の出席とする扱いについては、国から文書が発出され、教育支援センターと同様の扱いとし、在籍校での出席扱いとする方向性が示されており、学習機会の確保の一つの方法として認識しております。
夜間学級での支援を決定する仕組みや通学時の安全確保、教員、教室の確保といった課題もありますが、国の施策や他自治体の事例を参考に、具体的申請ごとに検討してまいりたいと思っております。最後に、新たな特例校の設置につきましては、教育振興基本計画のとおり、北沢小学校跡地での学びの多様化学校、不登校特例校の開校に注力いたします。その後の展開については、北沢での実施状況を踏まえた上でとなりますが、検討する際には、午後から授業を開始する昼間部と夜間部を併設する事例が他自治体で実施されているということから、こうした時間設定の学校への通学希望についても調査しながら、検討対象としてまいります。
いずれにいたしましても、体調が優れずに日常生活に支障がある児童生徒の学習機会を確保し、学びに向かえるように努めてまいりたいと思っております。以上です。
◆上川あや
夜間中学に関連して再質問いたします。
ようやく本区の夜間中学でも不登校学齢生徒の受入れに前向きな答弁が出たものと理解いたしました。
夜間中学の学びも排除しないというのであれば、ぜひ広報の改善を求めたいと思います。現在の区のホームページ、最新のせたがや便利帳、区教委発行の「せたがやの教育」のいずれの夜間中学の案内を見ましても、学齢期の生徒は対象外としか読めない広報しか行っておりません。改善を求めますけれども、いかがでしょうか。
◎宇都宮 教育総合センター長
再質問にお答えいたします。
議員より御紹介いただいた夜間学級への学齢生徒の登校は、学籍を変更するものではなく、在籍校との連携の下、生徒の学習機会を確保する支援策として実施するものです。
御指摘いただきました広報媒体につきましては、限られた紙面で正確性を期す見地から、夜間学級に学籍を置く上での基本的情報のみ掲載してきたことから、現在の表記となってしまっております。議員がお求めになっております文科省通知に基づく不登校生徒の夜間学級における支援についても、広報の在り方を検討してまいります。また、当事者、保護者、学校関係者が理解することが大事であることから、相談支援の案内の中で、起立性調節障害の症状の方にはどのような支援策があるのか、学校と支援機関で情報を共有するように努めてまいります。また、当事者や保護者に向けて、御自身の状況にとってどのような支援策があるのかを分かりやすくお知らせするように工夫してまいります。以上です。
◆上川あや
障害者施策の推進の担当のほうに伺いましたところ、世田谷区の障害理解の促進と地域共生社会の促進の条例によると、合理的配慮の提供義務の対象になる障害等、この等の中には起立性調節障害も含むというのが所管課の回答だったんですね。合理的配慮がない現在の設計では困りますので、しっかり教育委員会、御配慮をお願いいたします。