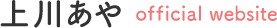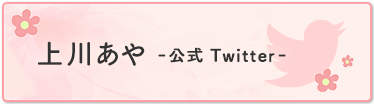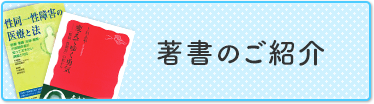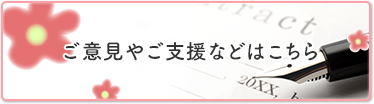◆上川あや
東京都職員共済組合、略称都共済の同性パートナー対応について伺います。
まず、なぜ区議会で都共済と疑問に思われる方もいらっしゃると思うので、一つ目の確認です。都共済の組合員には二十三区の常勤職員も含まれる。二十三区の常勤職員は自動的に組合員となり、給与額に応じた掛金も毎月天引きをされている。そういう理解でよいでしょうか。
◎須藤 総務部長
常時勤務に服することを要する地方公務員たる特別区の職員は、東京都職員共済組合の定款に基づいて組合員となります。その上で、共済組合の組合掛金を給与から控除されることとなります。
◆上川あや
都共済のホームページにはパートナーシップ宣誓制度の適用についてと題したページがあり、職員の同性パートナーにも利用可能な施設として次の五つが列挙されています。
箱根の温泉保養施設の固有名、浜松町の宿泊・婚礼・宴会施設の固有名、また、夏季、冬季の委託保養施設、リフレッシュ宿泊施設、清瀬市運動場が全てです。しかし、これら五つだけで果たして平等が担保されたと言えるのか大変疑問です。
そこで、次に確認したいのが、東京都のオリンピック憲章理念実現の条例第四条、都、都民及び事業者は、性自認及び性的指向を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならないと規定する事業者に都共済が当たるのかどうか、この点はいかがでしょうか。
◎須藤 総務部長
東京都職員共済組合につきましても、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例の第四条に規定する事業者であると認識しております。
◆上川あや
都共済も差別が禁止された事業者であることが確認できました。
次に、都共済のホームページでは、都共済の事業を大きく次の三つに区分できるとしています。一つ目に短期給付事業、二つ目に長期給付事業、三つ目にその他の福祉事業です。先ほど挙げた五つの施設は、三つ目の福祉事業のごく一部にすぎません。このうち一つ目の短期給付事業は、民間会社に働く方々が加入する健康保険に相当し、二つ目の長期給付事業は共済年金に当たる。また、三つ目の福祉事業も、基本は、地方公務員等共済組合法に規定のある組合員及びその被扶養者の福祉の向上に資するための事業ということです。このため、いずれの事業の対象も基本的には法の規定に縛られるという理解でよいのでしょうか。
◎須藤 総務部長
お話しのとおり、大きく三つの区分の事業がございます。
短期、長期の給付事業につきましては、地方公務員等共済組合法にその種類や給付の内容について直接規定をされており、東京都職員共済組合においても、これに基づき事業を実施しております。
また、福祉事業につきましても、共済組合が行うことのできる事業が法に規定されており、東京都職員共済組合の福祉事業につきましても、その多くは法に基づいた事業として行われているものというふうに認識してございます。
◆上川あや
「その多くは」と留保がつく点が重要だと思っています。
次に、同法が規定する被扶養者の範囲に事実婚の男女は含まれる一方で、同性パートナーは含まれず、排除をされてきた。以上の理解に誤りはないでしょうか。
◎須藤 総務部長
法で規定する被扶養者に事実婚の男女は含みますが、同性パートナーは含まれません。
◆上川あや
ところが、さきの五つの施設提供がそうであるように、全ての福祉事業で同性パートナーを排除するべきかといいますと、それも違います。その点をいま一度精査するべきだと考えます。
例えば、都共済ホームページが列挙する福祉事業の一つ、こころの相談事業の広報には、平易に、組合員だけではなく、御家族からの直接の御相談もお受けしていますと書かれています。ここでいう御家族に同性パートナーを含めたところで支障などないと考えるのですが、いかがでしょうか。
◎須藤 総務部長
こころの相談事業の対象につきましては、組合員及びその家族とされております。東京都職員共済組合では、家族の範囲は広く捉え、同性パートナーについても相談に応じているというふうに確認をしております。
◆上川あや
同性パートナーも家族と捉え、御相談が来れば応じている。福祉事業の対象にも拡大し得るということです。
であるならば、なぜ、さきに挙げたパートナーシップ宣誓制度の適用についてで御利用いただける事業、サービスとして書かないのでしょうか。法の明文で対象範囲が限定された事業でないならば、その広報も含め、職員の同性パートナーにひとしく開かれたものにしていただかなければ、本来、筋は通りません。
区には改めて各事業の精査と広報の見直しを進言いただきたいと考えているんですけれども、いかがでしょうか。
◎須藤 総務部長
事業の内容や対象となる方などについては、全ての組合員に丁寧かつ分かりやすく周知する必要があると考えております。利用が可能なものにつきましては、広報の仕方について検討いただけるよう、東京都職員共済組合に働きかけてまいります。
また、今後、法の規定によらず、共済組合の裁量の中で、同性パートナーを対象とする可能性がある事業がないかについても、区として改めて確認してまいります。
◆上川あや
最後に、根拠法が規定する事実婚の定義についても同性カップルは含まれ得ないのかどうか、再検証を求めたいと考えています。
三月、最高裁は、犯罪被害者遺族に支払われる国の給付金について、被害者と同性のパートナーも事実婚に該当し対象になり得るとする初めての判断を示しました。事実婚のパートナーを法律婚と同等に扱う規定は年金をはじめ多くあることから、この判断が他の法の解釈にも影響を与える可能性が指摘をされております。現に、住民票の事実婚の記載をめぐり、七月九日、総務大臣も、各制度の所管府省庁においても議論が進められていると理解していると述べて、検証途上であることを示唆しています。
この点を踏まえ、国への同法解釈の照会も含め、事業の在り方を検証、検討し、都と区で真の平等を目指した議論を深めていただく必要があると考えております。この点、区からも積極的に働きかけていただくよう求めますけれども、いかがでしょうか。
◎須藤 総務部長
世田谷区では、世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例を掲げまして、職員の休暇制度や給与制度、また職員互助組合の給付等において、同性パートナーも事実上の婚姻関係と同様に扱うよう拡充に取り組んできたところであります。本来は短期給付、長期給付とも含めまして同様に対応できるよう、法解釈の変更あるいは改正が行われることが望ましいものと考えております。
今後、委員お話しの最高裁の判決後、国への検討状況の照会と併せまして、より幅広い事業において同性パートナーも除外することはなく均等に処遇できるよう、東京都職員共済組合や区長会などを通じまして、要望、国への働きかけについても検討してまいります。
◆上川あや
私が求めるのは特権ではなくて、あくまでも平等です。
多様性尊重条例の第八条第五号は、性的マイノリティの性等の多様な性に対する理解の促進及び性の多様性に起因する日常生活の支障を取り除くための支援でありますから、足元にいる職員の平等が担保されていないということに着目をして、ぜひ世田谷区から率先して改めるよう進めてください。お願いいたします。
以上で終わります。