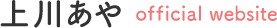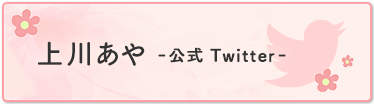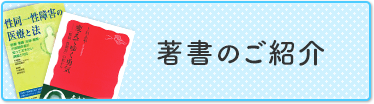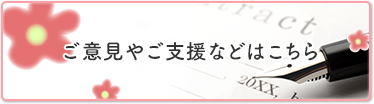◆上川あや
まず、私もその誕生に一役買いました世田谷区教委の服装自由の日、カジュアルデーについて伺います。
その誕生の経緯を当時の朝日新聞報道の一部抜粋から振り返ります。
世田谷区立の全中学校で二〇一九年度、好きな服装で登校できるカジュアルデーを設けることになった。カジュアルデーは、生徒自らが服装について考える日として月一回程度実施、授業に支障のない範囲で服装は自由でいいというもの。予算委員会で上川あや議員が、性同一性障害の生徒が制服着用の強要で不登校になった例を挙げ、着用は義務ではないことを学校現場に徹底させるべきではなどと質問した。堀教育長がカジュアルデーに言及し、生徒の主体的な判断と適切な自己表現を促すとともに、多様性を理解、尊重する機会とすることを目的とすると答弁。一九年度から全中学校で実施する予定を明らかにした。引用はここまでです。そこで、まず確認します。今、御紹介した質疑の日の御答弁では、いわゆる制服、区教委で言うところの標準服は学校推奨の服装ではあるものの、その着用は義務ではないという御答弁でした。この義務ではないとする部分、御認識に変化はないでしょうか。
◎山本 教育指導課長
その認識に変化はございません。
◆上川あや
その着用が義務ではないということが確認できました。
次に、カジュアルデーの開始から五年半が経過しましたが、この間、服装を自由としたことで大きなトラブル、また風紀の乱れ等あったでしょうか、問題は起きていないのではないでしょうか。
◎山本 教育指導課長
カジュアルデーは、生徒の主体的な判断と適切な自己表現を促すとともに、多様性を理解、尊重する機会とすることを目的として行い、毎月土曜授業での実施をしておりましたが、服装を自由にしたことによる大きなトラブルは聞いておりません。
◆上川あや
山本教育指導課長はそもそも制服がない都立の公立中学校、例えば杉並区立中学校の様子について耳にされてきたと伺っております。制服のない学校の先行例から見えてくる現場への評価はいかがでしょうか。
◎山本 教育指導課長
日常生活においては特に困ることはなく、決まり事がないことにより、教員が子どもたちを制服について指導することがないため、子どもたちとの関係が変にぎくしゃくすることが少ないように感じるということを聞きました。先行事例からは、標準服がないことにより生徒の主体的な判断と適切な自己表現を促すとともに、多様性を理解、尊重する機会になったという意見がある一方、式典や上級学校への訪問に際し、標準服があったほうがよいという意見もあり、賛否あると捉えております。
◆上川あや
区教委に伺うと、現在カジュアルデーは月一回ある土曜日授業の日が全校で実施日になっている。ところが、この土曜日授業も来年度から基本なくなるという認識なんですが、よろしいでしょうか。
◎山本 教育指導課長
委員お話しのとおり、カジュアルデーは現在毎月の土曜授業で実施しております。土曜授業の見直しについては世田谷区教育振興基本計画に示しており、来年度から振替休業日を設けない土曜授業については実施しないこととしております。学校行事や学校公開、地域行事等、必要に応じて振替休業日を設定した土曜授業は実施しますが、年間の実施回数は少なくなります。
◆上川あや
カジュアルデーを行う土曜日授業が振替休日を除いて原則なくなるということが確認できました。
そこで提案があります。カジュアルデーのそもそもの目的、生徒の主体的な判断と適切な自己表現を促すとともに、多様性を理解、尊重する機会とするその実践をもっと前に進めてよい時期だと考えるのです。全区立中学で服装自由の日を設けても問題は起きておらず、生徒は落ち着いている。制服を持たない区立中学の様子を聞いても、よい評価がある一方で、大きな問題や支障は見当たらない。ならば、生徒の主体的な判断に任せる日を何も月一日だけに限定する必要もないはずです。生徒と学校とで話合い、各校ごとの判断で拡大も可としていただきたいのです。話合いの結果、週三日でも、また、週五日の丸々でも私はいいと考えますが、いかがでしょうか。
◎山本 教育指導課長
世田谷区教育振興基本計画でも、子どもの声を聞くことを大切にしております。カジュアルデーについては、来年度以降、中学校で子どもに意見を聞き、子どもと大人が議論するなどして実施日数を含めた検討を行っていきます。この結果によっては、カジュアルデーを月一回の実施ではなく、拡大していくことも十分考えられます。
◆上川あや
区の子ども条例の一部を改正する条例素案の第五条は自分らしくいられる権利、また、第八条は自分で自分のことを決める権利となっていますよね。学校には、公式行事等、折り目をつけるべき日もあると考えますので、一気に標準服の廃止まで求めるつもりはないですけれども、子どもに合理的説明ができないような大人たちによる服装の画一的な強制は見直していくべきだと考えています。
今後は、いっそカジュアルデーを主体に、卒業式など特定の学校行事の日をフォーマルデーに設定し、TPOを考えるといった機会にしてもよいように考えるんですけれどもいかがでしょうか。
◎山本 教育指導課長
子どもとの話合いにおいて、カジュアルデーを主体に式典や行事において標準服の着用を求める声があれば、各学校とも十分に検討する必要があると考えております。その際には、学校外への訪問に際し、標準服が適している場面も想定されることや、職場体験先から標準服での体験を求められるケースもあることから、子どもだけではなく、保護者、地域や関係者の意見を聞いた上で、TPOに合わせた服装も、併せて丁寧に検討していくことが大切であると考えております。
◆上川あや
ともあれ、来年の新条例施行に合わせ、長らく教育現場で当然のこととされてきた服装という自己表現を、不合理な制約、半強制的な取扱いというものは脱ぎ捨てていただくよう求めたいと思っています。
最後に、区教委の今後の取組方針について伺います。
◎山本 教育指導課長
標準服の着用について様々な御意見をいただきました。カジュアルデーについて考えることは多様性を学ぶきっかけであり、御指摘いただいたことは従来からあるルールであっても、生徒とともに問い直す風土をつくることだと認識しております。教育委員会としましては、子どもの意見、考えを大切にし、各校における子どもの人権や個性を大切にした教育、学校づくりを進めてまいります。
◆上川あや
生徒指導のガイドブックとして位置づけられてきた文科省の生徒指導提要が二〇二二年、十二年ぶりに改訂となりました。そこでは、生徒指導の定義を、児童生徒が社会の中で自分らしく生きることができる存在へと、自発的・主体的に成長や発達する過程を支える教育活動のことであると書いており、非常に好感しています。これに照らせば、生徒一人一人の個性や自発性、主体性を無視した学校側による服装の押しつけはもはや卒業しなければならないものだろうと考えます。制服を着たい生徒は着ればよい、ただ、それを着たくない生徒にまで押しつける対応は誤りであって、これを改めていくべきだと考えておりますので、ぜひ生徒の声に耳を傾けて、その人らしい選択の幅を尊重するように現場を指導していただきたいと思います。
以上で終わります。