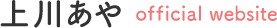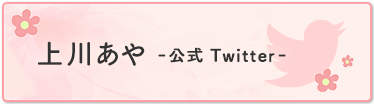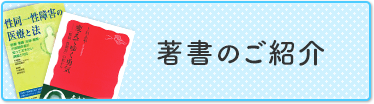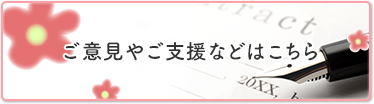◆上川あや
続けて、同性パートナーも家族として扱う医療機関の可視化、見える化についてです。
この質問はもう五回目です。何度も繰り返さざるを得ない現状がとても悲しいです。同性同士、家族として暮らしても、医療の現場に理解があるとは全く限らない。そんな実例を見聞きするたび、当事者の間には懸念が広がります。パートナーの健康が脅かされている重要局面で、診察や診断、告知に寄り添えない。家族として病状、容体の説明がされない。当人に代わって手術に同意はできず、危篤になってすら知らされない。果ては臨終への立会いすら認められない。男女の夫婦ならあり得ない排除が、現にそこかしこから伝えられてくるのが現状です。こうした悲劇が起きない区内医療機関の見える化を求め続けて五年。
ここ最近の区の御対応についてメモをいただきました。
昨年十月と十二月、区の職員が区内の二つの病院を個別に訪問し、対応を要請。また、本年四月にも同二病院を再度訪ねて、重ねて対応を御依頼。加えて、本年五月の世田谷区病院院長会では区の福祉人材育成・研修センターで実施する「セクシャルマイノリティの理解」研修への参加を御依頼にもなったということです。
こうした御努力には深く感謝する一方で、パートナーの性別が異なるだけで、なぜこうもフラットに御対応いただけないのだろうと悲しくならざるを得ないのですが、今後の見通しはいかがでしょうか。
◎小野 保健医療福祉推進課長
委員お話しのとおり、区ではこの間、関係所管と連携し、区内の病院院長会において、性的マイノリティーへの理解を重ねて依頼し、実際の医療現場での配慮や、性の多様性理解の研修への参加を依頼してまいりました。あわせて、これまで区内の複数の病院を実際に訪問し、同性パートナーへの対応についてホームページ等で広く公表していただけるよう、依頼を行ってまいりました。
しかし、いずれの病院も同性パートナーの方を家族同様に対応している旨の御説明はいただけたものの、ホームページ等での公表に関しましては、いまだ御承諾をいただけていない状況です。
相手方があることですので、いつまでにとは申し上げられませんが、区といたしましても、今後も病院院長会を通した働きかけを継続して行うとともに、機会を捉えて個別の区内医療機関へ訪問するなどの働きかけを行い、できる限り早期に実現できるよう取り組んでまいります。
◆上川あや
取組から五年たちました。区が内々に得ている感触は、決して後ろ向きなものばかりではないということは存じています。しかし、では、どの病院に救急搬送されれば家族として御対応いただけるのか、また、死に目に会えるのかは、まだ保証の限りではなく、全く分からない。この点、なかなかできない御様子に、区内の同性カップルの皆さんからは、当事者不在の中、両者で議論を進めても、医療現場の皆さんに現に起きているトラブル、また、そのニーズの切実さを御理解いただくのは難しいのではないか。自分たちの声を届けることが有効なら、ぜひ区とのタイアップを考えていただきたいという、そんな声も届いているのですけれども、どのようにお考えになるでしょうか。
◎小野 保健医療福祉推進課長
医療機関において、同性パートナーの方を家族同様に対応していただき、その対応について一般に広く公表していただくためには、医療機関の方々に実際に同性カップルを取り巻く状況や当事者の方々の思いなどを知っていただき、十分に御理解いただくことが重要であると認識しております。
区といたしましては、当事者の方々の思いをどのように医療の現場にいらっしゃる方々におつなぎできるかどうかを考えてまいります。まずは、区職員が当事者の方々の御意見をいただく場を設けるなど、同性カップルの方々が実際に医療現場において直面している問題や当事者の御要望などを十分に酌み取ってまいります。そして、それを踏まえた上で、引き続き病院院長会や個々の医療機関に対してより丁寧に説明し、対応を依頼するなど、粘り強く取り組んでまいります。
◆上川あや
御対応を平等にできると答えながらも、外向けに広報されたら困るという、この理屈が私は全く分からないです。
病院の実務レベルで同性パートナーの方がキーパーソンになり得ると、その後の退院調整、介護にもしっかりと平等対応が広がっていくと思いますので、この取組をしっかり改めていただくよう、改めて求めておきたいと思います。
以上で私の質疑を終わります。